「保育士を辞めたい…」限界を感じる7つの理由と退職を伝える時期・伝え方
Last Updated on 2025年10月10日 by yura

保育士の仕事は子どもたちの成長を支える大切な職業です。しかし、「もう限界かも…」と感じる方も少なくありません。
私も正社員で保育士をしていた時は、毎日「いつか絶対辞める」と思いながら働いていました。
この記事では、保育士が退職を考える主な理由と、退職するための方法を詳しく解説します。

保育士が限界を感じる7つの理由
人間関係のストレス
職員同士の上下関係や価値観の違いから職場の雰囲気が悪く、精神的に疲れてしまうことがあります。女性比率が高い職種というのもあり、「女性だけの職場なので気が楽」「セクハラが無い」という人もいれば、「陰湿ないじめがある」「同性に厳しい」などの意見も聞きます。
長時間労働と残業
勤務時間外でも保育日誌や保育計画の作成、行事準備などの業務が多く、残業・持ち帰り仕事が日常化している園もあります。仕事とプライベートの境界線が曖昧になり、心身ともに疲弊することが多いです。

知り合いの保育士さんで、毎日睡眠時間を削りながら持ち帰り仕事をしていたせいか、旦那さんから「一回仕事を辞めて少し休んでほしい」と言われて退職した方もいました…。
給与・待遇の不満
保育士の給与水準が低く、業務内容や責任の重さに見合わないと感じる人が多数います。賞与が少ない、昇給がほとんどないなど、待遇面で将来的な不安を感じてしまうケースもあります。
責任の重さ
保育士は子どもたちの命を預かる責任が伴います。小さなミスでも重大な事故につながりかねず、日々強いプレッシャーを感じながら働いているため、精神的に追い詰められることも少なくありません。
体力的な負担
子どもと一日中接する仕事のため、常に動き回る必要があります。抱っこやおんぶ、外遊びなどの肉体労働も多く、慢性的な腰痛や肩こりなどを引き起こす保育士も多いです。
また、感染症が流行りやすいので、子どもたちから病気をもらって体調不良になることもあります。
キャリアアップの難しさ
保育士として働き続けても、主任や園長などのポジションに空きが少なく、キャリアアップが難しいと感じる人もいます。また、経験年数が給与や待遇にあまり反映されず、責任だけが重くのしかかってくることもキャリア形成の障害になります。
保護者対応の難しさ
保護者の育児方針や教育観が多様化する中、一人ひとりの保護者の意向に沿った対応が求められます。保護者とのコミュニケーションの難しさやクレーム対応が心理的負担となり、仕事へのモチベーションを失う保育士もいます。
円満に退職するための方法

退職を決意したら、できる限りスムーズに円満退職を目指しましょう。
退職を伝える時期
クラス担任を持っている場合は、3月末の退職が望ましいでしょう。もし年度途中で辞めたい場合は、少なくとも行事が多い時期(運動会前、発表会前など)は避けた方が良いでしょう。
辞めたいと思ったら、園長や主任に余裕を持って伝えることが大切です。法律上では2週間前に退職を申し出れば大丈夫ですが、引継ぎや保育士の募集もあるので、退職希望日の3ヶ月前には伝えると良いでしょう。

退職理由を伝える
理由を伝える際はできるだけネガティブなことを言わず、「自分のキャリアアップや新たなチャレンジのため」と前向きに伝えましょう。
主な退職理由
- 介護・子育てのため
- 結婚のため(引っ越し・妊活など)
- 次の職場が決まっている
- 別の保育も経験してみたい
- 勉強のため(資格取得・職業訓練など)
家庭の事情が一番引き止めにくい理由だと思います。また、「小規模園で働いてみたい」「もっと自然とたくさん触れ合える園で働いてみたい」など、いろんな経験をしたいという理由も前向きな退職理由といえるでしょう。
例:キャリアチェンジの場合
「以前から関心のあった別の分野(例:病児保育など)に挑戦したいという思いが強くなり、このたび退職を決意いたしました。園での経験を糧に、次のステップに進みたいと考えています。」
引き継ぎを丁寧に行う
後任の保育士が決まっている場合は、担当している子どもや業務の引き継ぎを丁寧に行い、園や同僚の負担を減らしましょう。引き継ぎが丁寧であればあるほど、辞める際の印象は良くなります。
同僚や保護者への挨拶
退職が決まったら、同僚や担当する子どもの保護者に感謝の気持ちを丁寧に伝えると円満退職につながります。退職を伝えるタイミングは、上司(主任、園長先生など)と相談したうえで決めましょう。
挨拶の際は、退職する旨をお礼とともに伝えましょう。口頭に加えて、連絡帳やおたよりなどに一言書くのもよいですね。
職員・保護者への退職の挨拶例
職員への挨拶例
「このたび、私事ではありますが、一身上の都合により○月○日をもって退職させていただくこととなりました。年度途中での退職で、ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。短い間ではありましたが、温かくご指導いただき、心より感謝しております。園での経験は私の大きな財産となりました。今後の皆さまのご健康とご活躍をお祈り申し上げます。」
保護者への挨拶例(クラス便りや保護者会などで)
「保護者の皆さまへ
突然のお知らせとなり申し訳ありませんが、このたび一身上の都合により○月○日をもって退職させていただくことになりました。年度途中での退職となり、ご迷惑をおかけすることを大変申し訳なく思っております。短い間でしたが、お子さまの成長を見守ることができ、とても幸せな時間でした。至らぬ点も多かったかと思いますが、温かく見守っていただきありがとうございました。これからもお子さまの健やかな成長を心よりお祈り申し上げます。」
※挨拶は園の方針や保護者対応ルールに従って内容を調整してください。
退職時の事務的な手続き・必要書類
退職日が決まったら、以下のような書類の提出・返却、受け取りが必要になります。
提出が必要な書類
- 退職届または退職願(園指定の書式がある場所もあり)
- 健康保険証(家族分含めて返却)
- 制服・名札・鍵・IDカードなど貸与物
- 引き継ぎ資料・個人メモなど(任意)
受け取る書類(退職後に必要になるもの)
- 雇用保険被保険者証
- 離職票(ハローワークでの失業給付に必要)
- 源泉徴収票(確定申告や次の職場で必要)
- 年金手帳(紛失していなければ返却不要)
- 健康保険被保険者資格喪失証明書
書類の発行や受け取りに時間がかかることもあるため、退職日が近づいたら園に確認し、抜け漏れのないように準備しておきましょう。
自分で言い出しにくい場合は「退職代行」も検討する
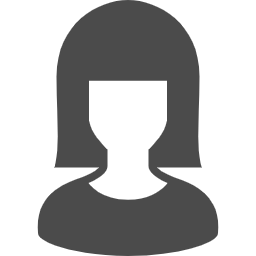
「辞めたい」と言っても引き止められる…
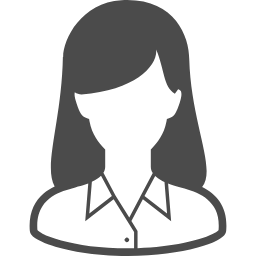
3月末まで耐えられないし、かといって年度途中は辞めにくい…
このような場合は、退職代行サービスを利用する方法もあります。
「職場に迷惑がかかるのでは…」と気にする方もいらっしゃるかもしれませんが、無断欠勤するよりよっぽどマシです。精神的負担を軽減し、スムーズに退職手続きを進めることができます。
弁護士法人ガイア法律事務所の退職代行なら、法的に認められた代理交渉が可能で、会社とのトラブルにも安心です。
まずは無料相談だけでも検討してみてください(LINEでの相談可能)。

まとめ

保育士を辞めることは決して悪いことではありません。心身ともに健康でいることが一番大切です。自分の限界を感じたら、無理せず新たな道を進んでいきましょう。
あなたが前向きな人生を送れるよう応援しています。






