園長が苦手・合わないと感じたら|嫌いな上司との向き合い方と転職の選択肢
Last Updated on 2025年10月3日 by yura
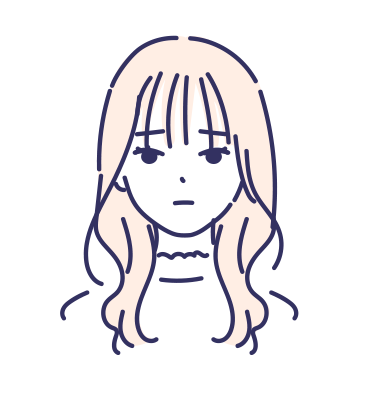
「どうしても園長と合わない…」
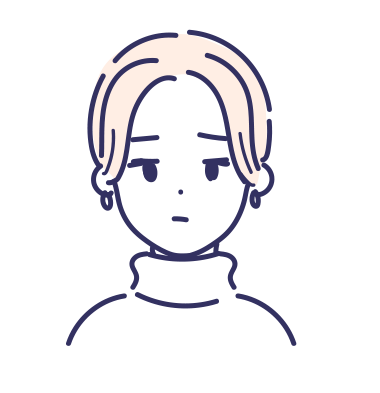
「正直、園長が嫌い…」
上司と合わないと、職場で働くのもつらいですよね。私もいろんな園を見ていますが、園長の人柄によって園の雰囲気も変わると思っています。
この記事では、園長との関係にストレスを感じる保育士さんに向けて、感情との向き合い方・状況別の対処法・転職という選択肢まで丁寧に解説します。

園長が苦手・合わないと感じる理由・対処法

保育の現場では、立場や年齢、価値観の違いから園長と合わないと感じる場面が多くあります。よくある理由は以下の通りです。
園長が独善的で意見を聞かない
園長が「自分の考えが絶対」と思っているタイプの場合、保育士の現場の声が届かず、フラストレーションを感じやすくなります。チームで働く保育現場において職員の意見を聞いてくれない姿勢は、職員の意欲を削ぎ、信頼関係の構築が難しくなります。
対処法
- まずは感情を込めすぎず、論理的に伝える方法を工夫してみましょう。「~すべき」という断定でなく、「~という意見も現場では出ていて…」などの緩やかな表現を意識します。
- 妥協案を模索してみて、園長の様子を伺うのも一つの手です。
- それでも変化が見られない場合は、「上司には意見が通らないもの」と割り切り、現場内での協力関係を強化することが精神的な逃げ道になります。
仕事を押し付けてくる
園長が、保育士に処理できない量の仕事を当然のように押し付けてくるケースがあります。たとえば…
- 行事の全体運営や準備を丸投げされる
- 書類業務や調整役を一方的に任される
- 他の職員が嫌がる仕事ばかり回ってくる
このような状態が続くと、業務量の偏りによって不満や疲労が蓄積され、「なんで私ばかり…」という思いが強くなります。園長自身が「適任だから任せている」と思っていても、実際には不公平な負担の押しつけであり、職場の公平性や信頼関係を損ねる要因になります。
対処法
- まずは「自分の仕事」を書き出してみましょう。自分がどのくらいの負担を背負っているのかを客観的に整理することで、対応の方針が立てやすくなります。
- 「ちょっとこれお願いね」といった曖昧な依頼が多い場合は、その都度きちんと確認しましょう。
- 定期的に仕事を押し付けられる場合、「今抱えている仕事の量」と「これ以上引き受けるのは難しい理由」を説明しましょう。例えば、「現在、〇〇と△△の準備で手一杯になっております。もし追加で対応する必要がある場合は、他の業務の優先度を調整させていただけると助かります。」と、このように「できません」と言い切るよりも、選択肢を提示してみましょう。
- もし「終わらない」と感じたら、早めに信頼できる先輩や上司に相談しましょう。
感情的な言動が多くて怖い
園長が感情に任せて怒鳴ったり、気分で対応が変わったりすると、毎日が「地雷を踏まないように気を付けよう」とストレスになってしまいます。これが続くと保育士側は常に緊張し、心身の不調をきたすこともあります。
対処法
- このタイプには反応しすぎないことが鉄則です。
- 感情的な言動が始まっても、「自分のせいではない」と冷静に受け流す力が必要です。
- 可能であれば物理的な距離を取ることや、会話内容を記録しておく(後の証拠保全)ことも対処策として有効です。
現場の保育士を理解してくれない

園長が現場の保育に関わっていない、または現場感覚を忘れている場合、現実と乖離した指示や方針が出されがちです。その結果、保育士が「なぜこんなに無理なことを言うの?」と感じ、信頼を失います。
対処法
- 感情的にならず、現場の声を定期的に共有する場(議事録、職員会議、個別報告)を持つことを提案しましょう
- 「現場は大変です」と訴えるのではなく、事実と数字で伝えると伝わりやすくなります。
- それでも無理解が続く場合は、別の上司に相談してみましょう。転職を検討するのも一つの案です。
パワハラ・モラハラ的な言動がある

人格否定・侮辱・無視などが継続的に行われる場合、それは明確なハラスメントです。「仕事だから仕方ない」と思い込み長期的に我慢すると、うつ症状や体調不良につながる恐れがあります。
対処法
- まずは記録を取る(日時・内容・状況)。感情ではなく、事実ベースのメモが重要です。
- 信頼できる上司や同僚、園外の第三者(労基署、教育委員会など)に相談する体制をつくってください。
- 転職を真剣に検討するタイミングでもあります。職場があなたの心と体を壊してまで続けるべき場所かどうかを、冷静に見つめ直しましょう。
園の方針に共感できない
「子どもを型にはめる保育」「形式重視で子どもの気持ちが無視されている」など、園の理念と自身の保育観がずれていると、どれだけ頑張っても心がすり減ってしまいます。
対処法
- 自分の保育観と園の方針との共通点がないか探す努力を一度はしてみましょう。
- それでも違和感が強いなら、「この園にいることで保育観が壊れてしまう」と感じる前に、価値観の合う園への転職を検討するのが健全です。
- 特に保育観に共感できる園を探すには、面接や園見学での質問項目を明確にしておくことが重要です。

と、まぁここまで色々書きましたが、正直話が通じない園長もいます。そんな園長の下で働くとなると、よっぽどの事が無い限り変わらないので、「園長と戦ってこの園を変える!」という方でなければ別の職場を探すことをおすすめします。
それでも園長と合わないときの対処法

距離を取る・接触を減らす
園長と直接関わる機会を減らすだけでも、心理的な負担は軽減されます。
例えば…
- 報告はメールやメモで済ませる
- 中間の主任を介して連絡する
- 会話は必要最小限にとどめる
他の保育士とのつながりを強化する
園長との関係が悪くても、他の先生たちとの関係が良好なら心の支えになります。
- 同僚と気持ちを共有する
- 職員同士でサポートし合う
- 孤立しないようにする
これだけでも職場に「居場所」ができ、耐えられる範囲が広がります。
証拠を確保し、外部機関に相談する
もし園長の言動にパワハラやモラハラの可能性を感じたら、まず優先すべきは自分を守ることです。証拠を確保しておくことは、万一、相談・通報・転職・法的対応が必要になった際に自分を守る有力な武器になります。
具体策:
- 罵倒・暴言・不当な叱責などを受けた日時・場所・発言内容を記録(手帳やスマホのメモなど)
- 可能であれば、録音アプリやボイスレコーダー等での記録
- 他の保育士が同席していた場合、証言協力の可否を相談しておく
- 事実を時系列でまとめておくことで、園外の第三者に説明しやすくなる
限界を感じたときに考えたい「転職」という選択
もしあなたが以下のような状況にあるなら、転職を検討してもよいタイミングです。
- 毎日出勤前に胃が痛くなる
- 園長とのやりとりで涙が出る
- 家に帰っても気持ちが休まらない
- 他の園で働くことを考える時間が増えてきた
- このままでは保育士を辞めたくなりそう
「環境を変える」という手段を持つことは、自分を守るための有効な選択です。
転職サービスをうまく活用する
保育士向け転職サイトを使えば、園の雰囲気や人間関係の情報も事前に得られることがあります。
レバウェル保育士なら、非公開求人多数、事前に職場の人間関係や評判も確認可能で、連絡手段も選べます(LINE・メール・電話)。
登録・利用は無料なので、「情報収集の一手段」として活用しても損はありません。

転職前に確認しておきたいポイント
転職を具体的に考える前に、以下の点を整理しましょう。
今の園の何が合わなかったのか明確にする
- 人間関係?
- 園の方針?
- 働き方?
何が原因だったのかを振り返ることで、次に選ぶ園での失敗を防げます。
自分が大切にしたい働き方を見直す
- 人間関係の穏やかな園?
- 書類仕事が少ない園?
- 子どもとの関わりを重視したい?
自分の希望を明確にすることで、求人票の見方や面接での質問の仕方も変わってきます。
まとめ|「園長が苦手」で辞めるのは甘えじゃない

園長が苦手、合わない、嫌い――
そう感じるのは、あなたが繊細で、他人に気を遣える優しい人だからこそです。
けれど、無理に我慢し続ける必要はありません。一度きりの人生、自分らしく働ける場所は必ずあります。
どうか自分を責めず、「もっといい場所があるかもしれない」と一歩踏み出してみてください。






