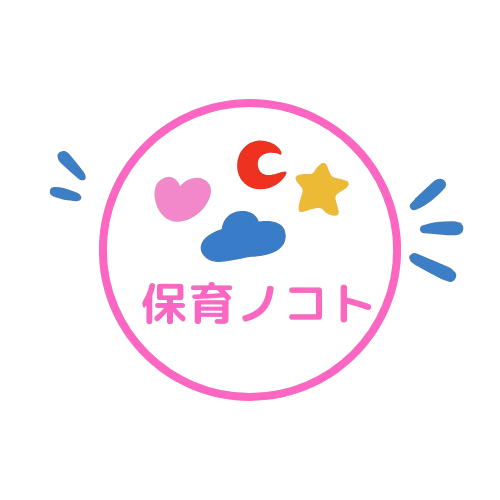「休憩なしでつらい…」保育士が辞めたいと感じる理由と今すぐ取るべき行動
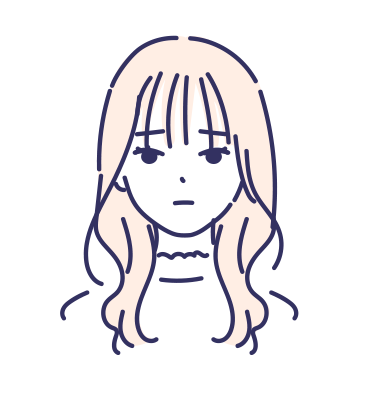
「朝から夕方までほとんど座る暇もない…」

「トイレに行く時間さえまともにとれない」
そんな状態が続くと、心身は確実にすり減っていきます。
私自身、正社員の保育士として勤務していた頃は、午睡中に昼食をかき込み、書類業務や製作・行事準備など、休憩時間を削って残っている仕事を終わらせようとしていました。
この記事では、休憩なしで働く保育士が辞めたいと感じる理由、今日からできる改善策、そして働きやすい園に出会うための行動について詳しく解説します。

保育士が休憩をとれない5つの理由

まず大前提として、本来は労働基準法で休憩が義務付けられています。(労働時間6時間以上=45分以上、8時間以上=60分以上の休憩)
しかし現場では、法律どおりにならない園が存在します。なぜ休憩が取れないのでしょうか。
保育士配置基準がギリギリ
日本の保育士配置基準は2024年度から一部改正されたとはいえ、国際的に見てもかなり厳しい水準です。休憩をとる余裕などなく、1人欠けるだけで運営がままならなくなる園も少なくありません。
実際には、休憩中でも園児に何かあれば戻って対応するのが現場の常識。
子どもたちの見守りが最優先

保育士の最も大きな使命は、「子どもたちの命と安全を守ること」です。そのため、常に目を離さず、即対応できる状態を保つことが求められます。
たとえば、園庭での自由遊びや散歩中でも、怪我や事故を未然に防ぐために神経を使い続ける必要があるため、一人でも保育から抜けられない状況というのが現実。結果として、「交代で休憩に入る」という簡単なローテーションすら組みにくい現実があります。
午睡中も見守り業務、書類業務がある
「午睡中=保育士の休憩時間」と見なされがちですが、実際にはそうではありません。
午睡中も、子どもの呼吸チェック・体位の調整・発熱の兆候の確認など、緊張感を持った見守り業務が続きます。
また同じ時間に、日誌や連絡帳の記入、制作・行事準備、玩具の消毒などの裏方作業を求められることもあり、身体も頭も決して休まりません。

子どもが寝ている間に終わらせないと、結局残業や持ち帰り仕事になってしまうので、午睡中も業務を進めます。
園による管理意識の低さ
「休憩はちゃんと取らせる」と言いつつ、実態管理はなし。園長や主任など管理職が職員の休憩取得を実質無視しているケースもあります。
本来、休憩時間は労働基準法第34条で「自由利用できる時間」と定められています。しかし現場では、仕事の延長線上であると見なされがちです。
休憩を取ることへの罪悪感
「忙しいのに私だけ抜けていいのかな…」「同僚に迷惑がかかるかも」
そう感じてしまう優しい保育士ほど、休憩を取れず、無意識に心身をすり減らしていることがあります。真面目で責任感の強い人ほど、自分を後回しにしてしまうのです。
休憩がとれないことで起こるリスクとは?
休憩が取れない状態が続くと、以下のような深刻な問題が発生します。
- 慢性的な疲労・倦怠感
- 判断力の低下による保育事故リスク
- 体調不良(膀胱炎・胃腸障害など)
- メンタルヘルスの悪化・燃え尽き症候群
保育士は命を預かる仕事。その大切な役割を果たすには、まず自分の心身の健康が不可欠です。
保育士の休憩を回すために必要な対策・選択肢

園全体で仕組みを見直す
職員間で共通認識を持ち、ローテーションで休憩時間を確保する運用など、業務フローの見直しが必要です。
- お昼休みを前後半に分けて必ず休憩する
- 書類作業は別時間に集中して行う仕組みにする
- 「今休憩いってきていいよ」と声かけが自然にできる雰囲気
などの対応が取れれば、負担はかなり軽減されます。
ICTの導入によって業務を効率化
日誌記録や連絡帳、午睡チェックなどを紙ベースで行っている園では、書類業務に多くの時間を取られています。保育ICTを導入することで業務時間を圧縮し、休憩時間を確保しやすくなります。
休憩取得の実績を可視化・管理
- 日ごとに誰が何分休憩できたかを記録
- 「今週はA先生だけ休めていない」と把握できる体制を作る
主観で「取れてるつもり」をなくし、客観的データで管理する園運営が求められます。
休憩は権利という認識の共有
- 労基法に則った説明を研修で行う
- 保育士自身も、休憩を取ることは自分を守る行為だということを認識する
「子ども第一=自分を犠牲にする」ではなく、自分の健康が子どもを守るという思考への転換が必要です。

私が勤めていた園でも「職員の休憩時間を確保しよう」という意識が高まり、職員の休憩室が作られてからは交代で休憩時間を取るようになりました。
園内で上司に相談する
園長や主任に、客観的に状況を伝えることが大切です。
- 書類に追われて休憩が取れていない
- トイレのタイミングすら取れない日が多い
など、感情的にならず事実ベースで訴えると、改善される可能性があります。
環境を変える=転職という選択肢
園内改善が見込めない、もしくはすでに限界を感じているなら、環境を変えることも立派な自己防衛です。今は保育士不足が深刻化しており、労働環境の整った保育園も増えています。
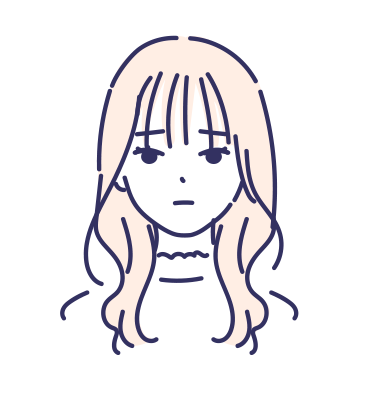
「でも、良い園がどこかなんて分からないし…」

「休憩の有無なんて面接では聞きづらい…」
そういう時は、内部情報を持っている転職サイトを活用する方が確実です。
レバウェル保育士なら、非公開求人多数、事前に職場の人間関係や評判も確認可能で、連絡手段も選べます(LINE・メール・電話)。

まとめ|あなたの「働きやすさ」は守る価値がある

保育士が休憩をとれないのは、あなたの甘えでも我慢が足りないからでもありません。
制度の未整備、職場の意識、文化の問題――つまり「環境要因」です。
まずは自分の健康と人生を大事にしてください。必要なら、環境を変えるという選択肢も十分に正当な行動です。
どうか無理をせず、あなたが本当に安心して働ける職場と出会えますように。