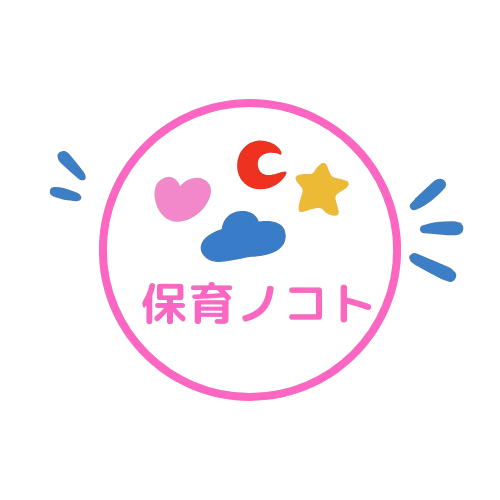保育士は一人暮らしができない?東京で一人暮らしをした保育士のリアルな生活費と支援まとめ

「保育士で一人暮らしなんてやっていけるの?」
そんな不安や疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。実際、保育士の給料は高くなく、特に都市部での一人暮らしとなると生活は決して楽ではありません。
結論、支援制度がある職場を選べば、保育士でも一人暮らしをしながら貯金もできます
今回は筆者が都内で一人暮らしをして、保育士の一人暮らしにおける制度の利用、リアルな生活費、実際に体験して分かったことまで具体的にご紹介していきます。

実際保育士って一人暮らしできるの?

結論から申し上げますと、「保育士でも一人暮らしは可能」です。
ただし、働く園の市区町村(自治体)にもよります。私が以前働いていた園では、「借り上げ社宅制度(保育士宿舎借り上げ支援制度)」があったので、その制度を利用して一人暮らしをしていました。
借り上げ社宅制度とは?
企業、運営法人(園)が、民間の賃貸住宅を借り上げて、それを従業員に「社宅」として提供する制度です。家賃の一部は自治体からの補助金でまかなわれ、従業員本人の自己負担は大幅に抑えられます。
特に東京都をはじめとする都市部での保育士不足対策としても、多くの園で導入されています。
筆者が利用していた借り上げ社宅制度の例
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給主体 | 自治体 |
| 利用対象 | 従業員(新卒・既卒どちらも対象) |
| 補助額 | 月額80,000円を上限 |
| 補助対象 | 家賃、共益費など。(更新料は従業員負担) |
| 条件 | 自治体が指定する保育施設での常勤勤務が必要。その他、様々な条件が決められている。 |
| 契約形態 | 園法人が借主(保育士は住人)、法人との契約終了で制度が無くなる可能性もある |

会社が所有する社宅と違って、一般の賃貸物件を利用するので職場の人と会う心配もなかったです。
保育士が利用できる主な家賃補助制度
国・自治体主導:「保育士宿舎借り上げ支援事業」
- 最大82,000円/月の補助(上限額・東京都基準)
- 補助割合:国=1/2、自治体=1/4、園=1/4が一般的
- 2025年度から「勤務開始から5年以内」までに短縮されるほか、継続利用は最長5年度に制限(自治体による)
- 自治体によっては「1人1回限り」の規定もあり

私が東京に住んでいた際に利用していた制度です。
継続利用が最長5年度(自治体による)というのがネックかもしれませんが、それでも5年間はかなり楽できると思います。
私は新卒の時は貯金ガチ勢だったので、手取り17万円でも毎月5~7万円ほど貯金していました。さらに新卒でもボーナスが出る職場だったので、新卒一年目で合計約90万円ほど貯金できました。
保育園独自の寮・社宅制度
- 保育園法人が所有・契約する寮や社宅に住み、家賃は1~3万円程度と格安
- 敷金・礼金が不要、駅チカや職場近隣物件が多い。
- ただし共同生活や掃除当番などのルールもあるため、生活スタイルとの相性要確認
保育園からの住宅手当(家賃補助)
- 自身で借りた賃貸物件に対して、毎月一定額または家賃の一定割合を補助
- 相場:月1〜3万円程度。
- 自由に居住地や物件を選べるメリットがあり、プライベートの制約が少ない
- ただし課税対象になる点や補助額は園ごとに差がある点には要注意
一人暮らしにかかる保育士の生活費の例(東京)

それでは、実際にどれくらいのお金がかかるのでしょうか。私が東京で働いていたときの実例を元に、月の生活費を公開します。
| 項目 | 金額(平均) |
|---|---|
| 家賃 | 7.5万円の物件を借り、借り上げ社宅制度で自己負担0円。更新料は2年に一度自己負担 |
| 食費 | 約3万円 |
| 光熱費(電気・水道・ガス) | 約1万円~1.5万円 |
| 通信費 | 約1万円 |
| 日用品・消耗品 | 約5,000円~1万円 |
| 被服・化粧品など | 約1万円~ |
| 交通費 | 自転車通勤だったので無し |
| 合計 | 約7万円~ |
→ 手取り月収:約170,000円(当時)
実際に感じた借り上げ社宅のメリット・デメリット
ここからは、私が「借り上げ社宅制度」を利用して感じたメリット・デメリットを紹介します。
メリット
- 初期費用がかなり抑えられた(敷金・礼金ほぼなし)
- 自分で物件を選べた(自転車通勤10分以内)
- 家賃が抑えられて貯金しやすかった

実際この制度が無ければ東京で一人暮らしは無理でした…
デメリット
- 契約は園の名義なので、転職や退職のタイミングで引越しが必須
- 特定自治体内に限られる(例:区内の園勤務が条件・園が契約している物件のみなど)
- 自治体によっては「1人1回限り」の規定もあり
- 継続利用年数に制限あり

私の時は継続利用年数は定められてなかったのですが、職場から「いつ制度が終了するか分からない」とのことだったので、万が一のために貯金を頑張っていました…。(結局私が働いている間はずっと続いていました)
保育士の借り上げ社宅制度(保育士宿舎借り上げ支援制度)では、2025年度から「勤務開始から5年以内」までに短縮されるほか、継続利用は最長5年度に制限するとのこと。(例外的に継続利用維持もあり)
この雇用年数の規程も、自治体によって独自の基準を定めていることがあり、借り上げ社宅制度を利用したい市区町村できちんと条件を確認しておくことが大切です。
借り上げ社宅制度を利用するには?
- 自治体の補助制度があるか確認
→ 「〇〇市 保育士 借り上げ社宅制度」などで検索 - 対応している保育園を探す
→ 保育士転職サイトで「借り上げ社宅あり」などの条件で検索可 - 面接時に詳細を確認する
→ 自己負担額・物件の自由度・退去条件などを必ず確認
家賃補助制度ありの職場に転職するなら…
レバウェル保育士なら、家賃補助制度がある職場を紹介してもらえます。また、非公開求人多数、事前に職場の人間関係や評判も確認可能で、連絡手段も選べます(LINE・メール・電話)。

最後に:あなたの生活を大切にする選択を

保育士の仕事は素晴らしいですが、それ以上に「あなた自身の生活」も同じくらい大切です。
私は一人暮らしを経験して、「自分の暮らしに責任を持つこと」「限られたお金でやりくりすること」の大切さを学びました。
今の職場では難しいと感じたら、家賃補助ありの園への転職も選択肢の一つです。
ぜひ、自分らしい働き方・暮らし方を見つけてください。