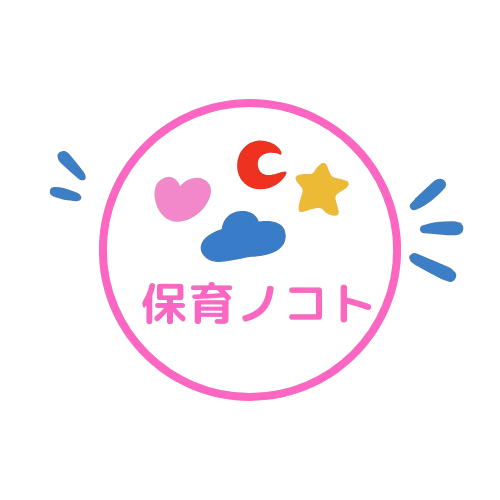「保育士なのに周りが見えてない…」と悩むあなたへ|改善のヒントと具体例

保育士として働き始めてしばらく経つのに、「周りが見えていない」と先輩や上司に言われる。子どもの様子や他の先生の動きに気づけず、自分だけ上手く動けない。
そんな風に悩む新人保育士の方は、実はとても多いです。
本記事では、保育士経験者の視点から「周りが見えていない」と言われた時の考え方や改善のヒント、そして実際に効果があった具体例を紹介します。

「周りが見えない」「視野が狭い」状態が続くと?

安全配慮の欠如
- 例:外遊びで危険な動きをしている子に気づかず、ケガにつながる
- 例:散歩中に後ろの子が列から外れても気づかない
➡ 安全管理が不十分になり、事故リスクが増加します。
子どものサインを見逃す
- 例:不機嫌や体調不良のサインを見逃してしまう
- 例:子ども同士のトラブルに気づくことができない
➡ 子どもの状態への気づきが遅れ、適切な対応ができなくなります。
チームワークの乱れ
- 例:他の職員が忙しいのに気づかず、自分の仕事だけしている
- 例:次の活動準備をしている先生がいるのに協力に入らない
➡ 「気が利かない人」「空気が読めない人」と誤解され、信頼関係に支障が出る場合があります。
連携ミス・情報伝達不足
- 例:共有事項に気づかず、誤った対応をする
- 例:他の職員の声かけやサインに気づけない
➡ 組織内の意思疎通に齟齬が生じ、トラブルの原因になります。
周りが見えない・視野が狭い保育士の主な特徴

全体が見えていない
特定の子どもに意識が集中しすぎるあまり、他の子どもの様子や集団全体の動きに気づけないという傾向があります。たとえば一人の子どものおむつ替えや着替えに集中しすぎて、他の子が危険な行動をしていても気づけない、あるいは他児のトラブルや不穏な雰囲気に反応できないという状況です。保育全体の安全を確保するうえではマイナスに作用する場合があります。
他の職員の動きに無関心・無反応
他の職員の動きに無関心だったり、連携を意識せずに行動してしまうという点も挙げられます。たとえば、周囲の保育士が片付けや次の活動準備で忙しくしているにもかかわらず、自分の作業だけを進めてしまい協力しないように見える、あるいは状況に応じたフォローや声掛けができずに「気が利かない」と受け取られるケースです。こうした場面が繰り返されると、チーム保育の中で孤立してしまう要因にもなりかねません。
場面の切り替えや時間配分が苦手
時間配分や活動の流れに対する意識が乏しく、マイペースに行動してしまうという特徴も見られます。日々の保育には「片付けの時間」「次の活動への移行時間」など、一定の時間感覚が求められますが、そうした切り替えが上手くできず、自分だけ活動が遅れたり、場面転換に気づかず動き出せなかったりする場面が多くなると、結果的に「周りが見えていない」と受け取られてしまいます。
なぜ「周りが見えない」と言われるのか?

保育現場でこの言葉が出る背景には、以下のような期待と現実のギャップがあります。
「周りが見えない=気が利かない」ではない
保育現場では、一人ひとりの子どもに寄り添いながら、全体の安全管理、他の職員との連携、行事準備や書類対応までマルチタスクが求められます。その中で、
- 他の先生が忙しそうなのに手伝わない
- 危険な動きをしている子どもに気づけない
- 時間に余裕がないことに気づかずマイペースに動いている
などの様子が続くと、「空気が読めない」「気が利かない」「周りが見えていない」と受け取られがちです。
見えていないのではなく余裕がないだけ
しかし、特に新人保育士の場合、多くは「見えていない」のではなく、「見る余裕がない」のが実情です。
- 自分の目の前の子どもに必死
- 失敗しないようにマニュアル通りにやることで精一杯
- 注意されないよう緊張していて視野が狭くなっている
これらは誰もが通る成長の過程であり、「能力が低い」というわけではありません。
改善のヒント

改善のヒント1:視野を「縦から横」へ広げる
新人時代は、目の前の子どもに集中する「縦の視野」になりがちです。まずは意識的に「横の視野」を持つようにすることが大切です。
実践例
- 子どもの行動を見ながら、周囲の音や気配も意識する
- 例:「あの子が泣いてる声が聞こえるな」「あそこに人が集まっているな」
- 担任の先生や先輩が今どんな動きをしているか注目する
- 例:「おやつの準備を始めてるから私もフォローしよう」
こうした小さな気づきの積み重ねが、「周りが見える力」になります。
改善のヒント2:動線と時間感覚を身につける
保育現場で「周りが見えている」と評価される人は、動線や時間配分にも敏感です。
意識するポイント
- 次に何が始まるかを常に頭に置く(例:あと10分でお昼寝 → トイレの声掛けを先に)
- 園内の動線・ルールを早めに覚える(例:おやつ配膳の順番や清掃のルール)
- 子どもが次にどう動くかを予測する(例:子どもが玩具に飽きてきた→次に走り出す可能性あり)
これらは経験とセットで身につくスキルですが、「次」を想像するクセをつけることで格段に改善します。
改善のヒント3:先輩の動き方を真似する
保育士はマニュアルより「現場の空気」で動く仕事です。そのため、先輩の動きを「観察」し「真似する」ことが、最短の学びになります。
具体的な観察ポイント
- どのタイミングで声をかけているか
- 子どもを見ながらどこに視線を配っているか
- 急な対応(ケガ・トラブル)時にどう動くか

実際に私も新人時代は、尊敬する先輩の動きを真似するようにしていました。「状況判断」「切り替えの速さ」「他職員への声掛け」が上手な人の行動には、いつもヒントが詰まっています。
改善のヒント4:「できてないこと」より「できたこと」に注目する
周りが見えないと注意されると、自分のミスばかりが目につきます。しかし、自己評価を下げすぎると萎縮してしまい、余計に視野が狭くなることも。
メンタル面のセルフケアも大切
- 今日は「◯◯に気づけた」「◯◯を手伝えた」と記録をつける
- 注意された内容を「次に活かすチェックリスト」に変える
- 失敗したときは、「次にどう動くか」だけに意識を向ける
自己否定よりも「改善意識」を持つことが、視野を広げる第一歩です。
それでも苦しいときは?

どうしても「周りが見えない」「視野が狭い」と言われ続けて自信をなくしてしまうような場合、今の職場環境そのものが自分に合っていない可能性もあります。特に、大規模な園や職員間の動きが複雑な職場では、新人やサポート職員にとって心理的・身体的な負担が大きくなることも少なくありません。
そういったときには、少人数でゆとりのある保育ができ、保育士一人ひとりの動きが整理されていて、協力体制も明確な園に転職することを考えてみるのもひとつの選択肢です。
| 状況 | 対応のヒント |
|---|---|
| 園の人間関係が悪く緊張し続けている | 園を変えることで改善する場合あり |
| 一人担任・即戦力を求められる職場 | サポートの多い職場に変える選択肢も |
| 自分のペースで保育がしたいタイプ | 少人数保育の園が向いている場合あり |
こうした「自分に合った園」を探すには、ただ求人票を見るだけではなく、園の規模や方針、保育のスタイルをしっかり比較検討できる転職支援サービスの活用がおすすめです。
レバウェル保育士なら、非公開求人多数、事前に職場の人間関係や評判も確認可能で、連絡手段も選べます(LINE・メール・電話)。
保育士以外の仕事を探している方には、こちらの記事もおすすめです↓


おわりに:視野は経験で広がる

「周りが見えない」と言われると、とても落ち込みます。でも、それは“見ようとしている”からこそ生まれる悩みでもあります。
今は見えなくても、経験を重ねれば自然と見えるようになっていきます。
どうしてもつらいときは、無理をせず環境を見直すことも必要です。最近は保育士向けの転職サイトや相談窓口も充実しています。ひとりで悩まず、支援を活用しながら自分らしい働き方を見つけてくださいね。