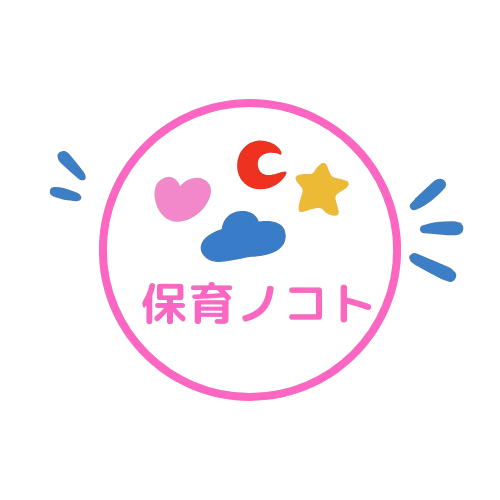保育士を辞めたくなる「保護者クレーム」への上手な向き合い方

保育士として働く中で、多くの人が経験するのが「保護者からのクレーム対応」。子どもへの対応や保育内容に対する意見などさまざまなことがクレームの対象になり得ます。
もちろん建設的なフィードバックもありますが、時に心をすり減らすような理不尽な内容や感情的な言葉で責められることも…。
この記事では、「保護者クレームに上手に向き合う方法」を解説します。

保育士が受けやすい保護者からのクレーム例

子どものケガ
例:
- 「ケガをしないよう、うちの子をしっかり見てほしい」
- ケガをさせた子の保護者から謝罪がない
- 事前に伝え漏れていた、または連絡帳に記載しただけで口頭での説明がなかった。
対応のポイント
- 即座に謝罪し、経緯を丁寧に説明
- あくまでこちらが悪いという姿勢
- 対応に不安があれば、園長や主任に相談する
もちろんケガをしないよう安全第一で子どもを見ることが当たり前です。
しかし、元気よく外で遊んでいるときに転んでケガをしたり、子ども同士のトラブルでケガをすることも。心配する保護者の気持ちも分かりますが、「うちの子にケガをさせないで」というのは骨が折れますよね。保育士自身も「ケガをさせてしまった」という自責の念にかられることも。

私もクラスで毎日のように子どもの噛みつきがあった時期がありました(しかも嚙まれる子は大体同じ)。その度に本当に申し訳ない気持ちになりながら謝罪をしていました…。
体調不良時の対応
例:
- 「微熱ですぐにお迎え依頼が来るのは仕事に支障が出る」
- 「家では元気でした」
対応のポイント
- 園としての発熱時の連絡基準を明示し、入園時や年度初めにしっかり周知する
- 呼び出しがあった日は、症状の変化と時間経過を記録し、次回以降の対応に活かす
- 「お仕事中に何度もご負担をおかけして申し訳ありません」と共感を含めた対応を
- 一部の家庭で過度な要望がある場合は、園長など管理職が対応する体制が必要
共働き世帯にとって頻繁な呼び出しは業務上大きな負担となりますが、園側としては他の子に感染する可能性があるので、連絡せざるを得ないですよね。
園の「安全重視の判断」と保護者の「家庭で様子を見られるレベル」の温度差が原因ですれ違ったり、一律の基準があっても保護者の感覚は人それぞれで納得されにくいことも。
行事に関するクレーム
例:
- 「なぜうちの子が発表会の中心になれなかったのか納得できない」
- 「仕事の都合があるので行事の日程を変えてほしい」
対応のポイント
- 配役や日程決定のプロセスをあらかじめ全体に対して丁寧に説明しておく
- 「子ども全員に成長の機会を」「公平な観点で決定した」という保育方針に基づく判断であることを伝える
- 日程変更の要求には、「全家庭への公平性」「会場・職員配置の制限」などを理由に丁寧に断る
親の期待や事情に寄り添う姿勢は見せつつも、一部保護者の要求に個別対応を繰り返すと運営が破綻するので、対応を保育士個人に任せず、園全体で対応方針を共有しましょう。
上手な向き合い方・対応策

一人で抱え込まず、必ず相談・共有する
まずは絶対上司に相談しましょう。「報告・連絡・相談」は基本です。
- 複数の視点で事実確認ができる
- 園長や主任が対応してくれることで安心感を得られる
- 同じようなクレームが続く場合、園全体で改善に取り組める
理想は、「クレームが入ったらすぐに報告・相談」という園内ルールが機能していることです。
もし今の園で相談しにくい・責任を押し付けられるような空気があるなら、環境を変える必要があるのかもしれません。
“事実”と“感情”を分けて受け止める
保護者からクレームを受けたとき、「感情に飲み込まれない」ことが大切です。
- 事実としての指摘:連絡帳に記入ミスがあった、報告が遅れたなど。
- 保護者の感情的な不満:「前から思ってたんですけど」「どうしてそんなことに?」など。
クレームには事実に基づく部分と、感情のはけ口としての側面があります。感情的な部分に反応してしまうと心が疲弊してしまいます。
言葉の選び方・記録の残し方を工夫する
保護者とのやりとりの中で、「伝え方」は非常に重要です。何気ない一言がクレームにつながることもあるため、慎重さが求められます。
- 連絡帳では主観的な表現を避ける(例:「今日はわがままだった」→「今日は〇〇に対して強く自己主張する姿が見られました」)
- 報告・連絡・相談は必ず記録に残す
- 口頭のやりとりもメモしておく(日時・内容・相手の反応)
また、クレームになりそうな出来事があった日は、先に連絡しておくことでトラブルの未然防止につながります。
「保護者対応のルール」がある園を選ぶ
多くのクレームは「組織的な対応体制が整っていない園」で発生・拡大します。
例えば以下のような園は、個人の対応力に依存しすぎており、保育士への負担が大きくなります。
- クレームがあっても上司が出てこない
- 園としての方針があいまい
- 書面での対応マニュアルが存在しない
もし園見学をする際には、「保護者対応は園全体で取り組んでいるか」という点を必ず確認しましょう。
つらさを言葉にして、整理する
保育士としてクレーム対応に直面したとき、どれだけ冷静に対応していても心の中では「責められている」「自分が悪いのかもしれない」と自責の念に駆られることがあります。モヤモヤが残っているときは、紙に書く、信頼できる人に話す、スマホのメモに打ち込むなど、言語化するだけでも気持ちは整理されやすくなります。
言葉にした瞬間、
- 「これは理不尽だったんだな」
- 「自分なりによくやってたんだ」
- 「次はこうすればいいかも」
という“気づき”が生まれ、ネガティブな感情に飲み込まれにくくなります。
時には転職という選択肢も
クレーム対応が日常化し、精神的に追い詰められている場合、「辞める」「転職する」という選択は決して逃げではありません。むしろ、それは「自分の命を守る行動」です。
世の中には、保護者対応を組織で考え、保育士のメンタルケアを重視する園もたくさんあります。
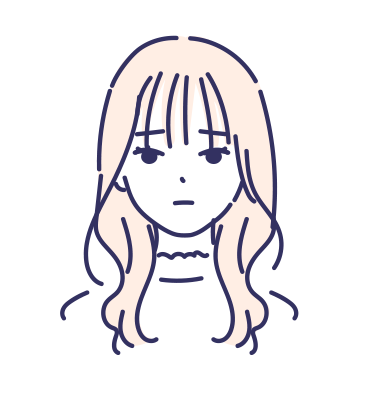
でも、良い園がどこかなんて分からないし…
レバウェル保育士なら、非公開求人多数、事前に職場の人間関係や評判も確認可能で、連絡手段も選べます(LINE・メール・電話)。
「転職=今すぐ辞める」ではありません。情報収集や年収シミュレーションとして、転職サイトに登録してみましょう。あなたの希望条件を伝えるだけで、求人を無料で紹介してもらえます。

まとめ

保育士にとって、保護者対応は避けて通れないものです。
しかし、その対応を「園が一人に押し付ける」のか「チームで支える」のかによって、働きやすさは大きく異なります。
保育士として「頑張りたい」「子どもと関わりたい」と思う気持ちはクレーム一つで消えるべきものではありません。
もし今の園での働き方に限界を感じているなら「辞める=終わり」ではなく、「次に進む第一歩」と捉えてみてください。